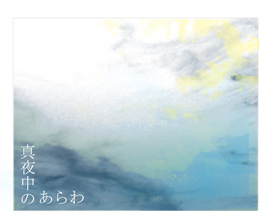 「よっ、と」 二階のベランダの欄干に足をかけて勢いよく飛び降りれば、ぐにゃりと足裏にめりこむ土の感触を感じた。すぐにつん、と鼻につたわる、庭草の濃い緑の香り、そうして体にまといつく夜の生暖かい空気。踵あたりについた土をパンパンとはらって空を見上げれば、またたく満点の星空が頭上にひろがっていた。素足にはいたハイカットのコンバースの踝が寒いけれど、あたしはパーカーのジッパーを上げて慎重に音をたてないように、裏口の扉からこっそりと忍び足で抜け出す。ちらりと自分が今飛び降りた自室のベランダを一回見やって、誰も起きず、誰も追いかけてこないのを確かめてから「ひゃっほー」とあたしは春の夜へと駆け出した。 ぐんぐんと勢いをつけて走れば頭上に咲くピンク色の花びらがきれいに舞った。 それに気を良くしながらも、すぐに「ぐ〜」とうるさく鳴った自分のお腹の音に笑う。 高校に上がったばかりの娘を心配する我が親の過保護ぶりは、夜のコンビニへの買い物ですらもお伺いをたてねばならない始末で、例えばこんな桜が満開に咲く素敵な真夜中にひとり空腹をおぼえても、99%の確率で「外出は駄目」とすっぱり切られてしまうのだ。そしてもうとっくに両親が寝てしまった今となっては、その確率は100%となってあたしは自室での葛藤のすえ(5秒ぐらいだったけど)あっさりと空腹に負けてベランダから飛び降りる事を選んだ。冷蔵庫をあさるという手もあったのだけれど、15歳の女の子が深夜の冷蔵庫前で「これはまだ賞味期限が切れてないよね……?」と確認する姿はわびしいもので、それにうちの冷蔵庫にはからあげくんも肉まんも入っていない。 ちゃりんちゃりんと小銭がポケットの中で子気味よく音をたてて「これで何を買おうかなー?」とあたしはうきうきとしながら駅前の24時間のコンビニエンスストアまでの坂道を走った。 元気に明かりが点いたガラス張りの店前までたどりついた時、その向こう側の歩道から、知ったような長身が歩いて来て、あたしは思わずドアノブに手をかけたまま暗闇に目をこらす。 「ん?………あれは」 「?」 夜に溶けるような涼しい声があたしの名前を読んで「あっ!」とあたしは同じクラスの柳蓮二くんが、身軽な格好でこちらに歩いて来ている事を認めた。 「買い物?」 「ああ、そうだ」 目の前でさらりとした細い髪がゆれて、柳くんはジーンズに包まれた長い足を止めてあたしの前に立った。開きかけたコンビニの店内から流れ出る、お気楽な軽いJ-popの曲調が「こんばんは」ときれいに挨拶をする柳くんと全然合わず、あたしは「えーと……こんばんは」と曖昧な返事をして彼を見上げた。 まだ二週間ぐらいしか柳くんと同じ教室で授業を受けていないけれど、彼は大半の女の子に初対面2秒で好感を持たれる隣のクラスの丸井くんや仁王くんと違って、表立って騒がれる事はない。けれど、みんな密かに心の奥で「いいな」と思っているタイプの男の子だ。もし恋バナの時に誰かがこっそり「柳くんもいいと思わない?」って言いだせば「実はあたしも……」「あっ、あたしも」なーんてうち明けちゃう感じの(そして大抵その会話は「あたしが一番先にいいなと思っていたんだから」という女子の不毛なプライドの戦いへと発展するんだけど)そんな和の雰囲気が漂う大人ぽい男の子なのだ。その柳くんが弁当を暖めるチーンという間抜けな電子レンジ音が鳴るコンビニ………… 「意外か?」 「えっ!?」 まるでそんなあたしの心を読んだかの様に柳くんは言った。 「普段利用する事はないんだが、今夜は緊急でな」 「へーそうなんだ、文房具とか?あっ、それか本?」 「腹痛だ」 「え?」 「姉がな」と言って柳くんはドアを開けて「入るのだろう?」とあたしを促した。いらっしゃいませーと間延びした声が響いてあたし達ふたりは店内の明るい照明に迎えられる。 「腹痛って」 「生憎と痛み止めを切らしてしまったらしくてな」 「そっか、それでお姉さんのかわりに?」 「そうだ」 「えっらいねー」 「夜道を一人で歩かせるわけにはいかないからな」 感心するあたしにさらっとそう言って、別にその事で何か偉ぶりたい風でもなく、柳くんは携帯用の酔い止めや簡単な薬などが売られているコーナーへと足を向けた。店内の時計を見れば、もう午前1時を回っている、背の高い後ろ姿をながめてこの薄暗い夜道をお姉さんが痛むお腹をかかえて歩かなくても済むように、かわりに歩いて来た柳くんを思って、なんだかあたしの中で彼への好感度が急激に上昇した。想像だけど、きっと柳くんは家でも所謂“男の役割”みたいなものを、苦もなくいつも引き受けているんだろう。(これをクラスの女子に言ったらもしかしたら彼の人気は表立って騒がれるレベルになるかも、あっでもまた誰かが「やっぱりあたしが思ってた通りー」とか言い出すなー)なんて考えてたら先程の自分の言葉が、なぜかあたしに当てはまらなかった事を不可解に思った柳くんが問いかけてきた 「そういえばは一人で歩いて来たのか?」 「えーと、あたしは…………」 残念ながらうちには年の離れた姉しかおらず、姉の為を思って夜道を歩いてくれる可愛い弟も生まれてくれなかった。「お腹が痛い」と言ったらお約束のように「食べすぎ」という返事が帰ってくる全員がボケとツッコミの役割分担だけはしっかりわかっている家族だ。でもその事を目の前の姉思いのカッコいい弟にここで言う気は、しない。空腹に堪えかねて、とベランダからの大脱走を正直に話したら柳くんが口の端を上げて笑った。 「玄関から出るという方法は考えつかなかったのか?」 「いやーうちの玄関立て付けが悪くってさー、音でバレちゃうんだ」 「だからあまり見ない格好なんだな」 「?」 「服だ、かなり軽装だからな」 「あっ、そっか」 あらためて自分のパーカーにジーンズ、足元はスニーカーという男の子みたいな格好を見て気づく。 そういえば学校の制服でも最初の校外学習の私服でも、けっこう気を使って女の子らしい格好してたな。 「似合わない………かな?」 「いや、新鮮だ」 あの耳障りの良い声で言って、すっと手元の薬棚に視線を戻した柳くんにあたしは迂闊にもどっきんとときめく。騒ぐ心臓をおさえて「やっぱお姉さんがいる男の子はナチュラルにキラーだな」と思った。深夜のコンビニに若い男女ふたり、ボトル飲料がならぶガラスケースにあたし達がゆらゆらと写っている。柳くんは良いと言ってくれたけどやっぱりその姿はせいぜい友達止まりで、カップルには見えなくて「柳くんが来るとわかってたらスカートぐらい履いて来たのにな、ちぇ」と思ったあたしはその後に「あっ、でもそれだったらパンツ丸出しでベランダ飛び降りなきゃいけなかった」と慌てる。 「いつもの格好も好ましいと思うが」 薬のパッケージを見ながら付け足すようにさらりと言ってのけた柳くん。 やっぱりパンツ丸出しで飛び降りても良かったかも。 本気でそう思う。 ふらり、ふらりと店内にある総菜やパンなどをながめて、最終的にあたしはねぎととろろが一杯のったおそばを選んだ。柳くんを見ていたら、なんとなく食べたくなったのだ。薬コーナーを見れば柳くんが通常のパッケージと朱色のパッケージの間で長い指をさまよわせていた。迷うなんてめずらしい、けれど手元をちらりと覗き込んで納得した…………多分どんな男の子でも、それは迷う。一瞬の間、細い指先が無印の方を避けて、コトリと「女性の体に優しい」と書かれた朱色の方を抜き取った。あたしの中でその優しさにどっきんと再度心臓が鳴る。レジに並んで立つ時、ピッと会計されてゆく朱色になぜだかあたしが柳くんのかわりにドキマギしたけど、思春期の少年の気恥ずかしさよりもやはり姉の体を思いやった柳くんに、あたしの中の彼への好感度はだだ上がるのだ。 「、一人で帰れるのか?」 店を出た後、そう問いかけてくれる柳くんに名残惜しさを感じつつもあたしは気丈にふるまう。 この深夜のサプライズが終わるのが、ただちょっと残念だ。 「うん、全然だいじょうぶ、近いし走って帰るし」 「また玄関は使わずに二階からか」 「まっさかーさすがによじ上りはしないよ、そぉ〜と慎重に玄関から入るって」 「そうか、それなら良いんだが」 「あたしの事は気にしなくて良いよ、柳くんは早くお姉さんに薬持ってってやんな」 「………そうだな、すまない、ありがとう」 「いいって、いいって」 そう自分でカッコよく言って「柳くん気を使ってくれてるなーやっぱ優しーなー」とほくほくと思いつつ、ポケットに手をつっこんだ時、ちゃりんと鳴ったコイン“だけ”の音にあたしはかなりな衝撃と共に奇声を上げた。 「ああっ!?」 その奇声で歩きかけていた柳くんが振り返った。 まさか、まさか、いや、そんなはずは、でも ……………………………ない。 「?」 「えーと………」 「大体の予想はつくが」 「………あはは」 「忘れた、落とした、なくした、どれだ?」 「(なんでわかるんだろう?)………多分忘れた」 「多分?」 「うん、多分、あっでも落としたんなら帰り道に絶対あるから見つかるよ!」 ぐるりと柳くんが首をあたしが来た方向にむけて、何か思案する顔になった。 あたしもそちらを見れば、深夜1時半近くのその道は足元もさだかではない真っ暗闇に包まれていた。 「うっ……」 「確率を言おうか?」 「え!?」 「鍵が見つかる確率」 「い、いや、結構です!」 どうにも鍵が見つかりそうにない暗闇を見て、あたしは自分のうっかりさを呪いながら、しかしこれ以上柳くんを引き止めるわけにはいかないと思って努めて明るい声を出した。 「確か鍵はちがう服にそのまま入れてた気がするし、それにうちお姉ちゃんが夜勤でもうすぐ戻ってくるから、玄関で待ってればそのうち帰ってくるよ」 「両親を起こして開けてもらうという手はないのか?今夜だけならそう怒られまい」 「えーと、それは…………」 「………………」 「………………」 「前科があるんだな?」 「ハイ………」 がくりと肩を落としてあたしは以前同じように夜に抜け出し、それが見つかってめちゃくちゃ怒られた事を思い出した。 「お前の姉が帰ってくるのは何時頃だ?」 「もうすぐだよ、うん」 「何時だ?」 「………えーと、あと数時…間?」 「正直に」 「………6時過ぎぐらいです」 ちらっと右手の時計に目をやって「あと5時間近くか」と言って柳くんはふうと溜息をついた。空腹に負けた自分が情けなく、こんな自分のうっかりに柳くんを付き合わせている事が申し訳なく、ぎゅっととろろそばの入った袋を握りしめあたしは「ほんとに大丈夫だから!また学校でね!」と言ってそのままくるりと背中を向けて駆け出そうとした。 「待て、」 涼しい声が飛んで来てあたしを呼び止める。 振り返れば柳くんが手をひらひらとふっていた。 ん?何………え? おいでおいで? 「うちに来い」 さらりと言って柳くんは面食らったあたしにちょいちょいと手招きをした。 「6時近くまで待っていれば良い」 「い、いや、それは悪いよ、柳くん本当に気にせず帰りなって、お姉さんが待って…………」 「姉も心配だが、俺はお前がこのまま暗闇で数時間待って風邪を引くか、暴漢に襲われるかするのも心配なんだ」 「う…………」 「いずれにせよ、食うのだろう?それ」 あたしの手元のとろろそばを差して柳くんはやわらかく笑って言った。 「茶も出そう」 柳くんのありがたすぎる申し出に、まだ「うーん」と遠慮して煮え切らず、返事をしぶる。しかしその良い子ぶりっこに一瞬で駄目だしをかける音が。 ぐ〜〜〜〜 「………フッ、茶菓子もな」 お腹をおさえて赤面し、こくこくと頷くあたしに笑って柳くんは先に立ち、歩き始めた。 ひらり、ひらり、と頭上から桜の花びらが舞い降りて、その中を柳くんの後をついて、てくてくと歩く。辺りは真っ暗で柳くんの背中とその肩に落ちる花びらしか、あたしの先には見えないけれど、時々振り返って歩調をゆるめてくれる柳くんがなんだかとても心強く、やっぱり一人であの真っ暗な道を帰るのはちょっと怖かったな、と今更ながら思う。 たどり着いた柳家は、立派な日本家屋だった。 「へーここなんだ」 「静かにな」 「はーい」 「お邪魔します」と心の中で小さく言ってあたしは玄関に上がった。奥の襖が開いて「蓮二くん?帰ったの?」と細い女の人の声がした。柳くんはそちらに行き、手に持っていた薬を渡して何か二、三言つげた。ちらりと視線を感じて、数秒後にくすりと笑い声がして「わかった、お父さん達もう寝たから、見つからないようにね」と悪戯っぽく言う声が聞こえた。 「台所に行こう、茶を出す」 「うん…」 「どうした?」 「顔とかみてないけど、柳くんのお姉さんてやっぱ少し柳くんと似てるね」 「なぜそう思う?」 「いや、なんか詮索しない所とか」 「フッ、だが驚かれたよ」 「え?」 「可愛い女の子を拾ってくるとは思わなかった、とさ」 「っ!?」 「……やっぱり似てるよ」 「そうか?」 「ちょっと心臓に悪い事いきなり言うトコとか」 「そうかもな」 しらっと言って柳くんは通してくれた台所で、ほうじ茶、緑茶、玄米茶、色々な日本茶をどれにするか聞き、最終的にあたしは玄米茶を選んだ。そわそわと腰を下ろした木の椅子は座り心地がよく、いつも柳くんはここで食事しているんだなーと感慨深く思った。柳くんがきれいな手つきで入れてくれたお茶を一口飲んで、パリパリとそばの包装を破いて、あたしは両手を合わせて「いただきます」と小さく言った。柳くんがそれに答えるように「どうぞ」と言って茶菓子も出してくれた。あたしがそばを啜っている間、柳くんは何も言わずただお茶をゆっくりと飲んでいた、深夜2時近くの台所にはずずーとそばを啜る音と、香ばしい玄米茶の香りと、柳くんがただそこにいて、でもそれが別に気詰まりでもなくて、あたしはただ湯のみを包む柳くんの大きな手に見蕩れていた。 「…なんかシュールだな」 「何がだ?」 「一時間前まで自分の家でぼ〜としながらお腹すいたなーて思っていたのに、今じゃ柳くん家で向かい合って、そば食べたり、お茶飲んだりしてるなんて」 「確かにな」 「予想もしてなかったよ、誰かに言ったら羨ましがられるな、こりゃ」 「なぜだ?」 「えーと、だって柳くんだからさ」 「なぜ“俺”だからなんだ?」 普通にそう聞き返す柳くんに、あたしは返事に困る。別に他意はなさそうだけど、自覚もなさそうだ。でもなんてたって一言から百ぐらいの情報は引き出せる柳くんだ。うっかり口を滑らせて、ちょっと好意があるなんて知られたら、ただでさえ深夜にヅカヅカと家に上がり込んでる身としては気恥ずかしい。 「クラスの子達で話してる時に、柳くんいいよねて話題がちらっと出たんだよ、うん」 「ほう、それは初耳だな」 「他にも、隣のクラスの丸井くんや仁王くんもカッコいいよねーて話になってさ」 「ふむ」 「入学したての頃によくあるどっち派?みたいな軽いガールズトークだよ」 「そうか」 「うんうん、柳くん人気あるんだよ、おめでと!」 「はその場にいたのだな?」 「そうだよ」 「で、お前はどっち派だったのだ?」 「うっ……!」 頬杖をついて、うっすらと柳くんは笑っている。 前言撤回。 他意がないなんて、嘘だ。 「えーと、それは」 「軽いガールズトークだったのだろう?」 手元のそばの最後の一口をぐるぐると箸で何度もつゆにつけたりしながら返事を逡巡する。 この二人きりの状態で、その見透かすような目でじっと見つめるのはずるいと思う。 「それはそうだけど」 「言いにくい、という事は俺ではなかったと推測するが?」 「いや、そんな事はっ………!(ガタン!)」 「フっ」 「あっ…!」 「席を立つぐらいの事か?」 「…………(恥ずかしい)」 「落ちてるぞ?」 「え?」 「とろろが」 「あっ!?」 机に落ちたとろろをティッシュで拭いて、最後のそばの一口をなんとか口に放り込んだ。負け惜しみながらも柳くんを軽く睨む。 「誘導尋問反対」 「なんとでも」 薄く笑ってそう言い、何事もなかったかのように「食べ終えたなら上にいこう」と柳くんは促した。茶菓子をふたつあたしの手に持たせ、柳くんは客室と思われる部屋から毛布やらを引っぱりだして来た。 「え?あたし寝ないよ?」 「わかっている、だが上の俺の部屋は寒いんだ」 「いや、ほんと玄関とかで待たせてもらうだけでも良いし、お茶も頂いたし」 「それだと下に寝ている両親に見つかってしまうのでな、別に良いのだが、後々説明が面倒だ」 「そっか、あっでも寒いんなら柳くん使うもんね、それ」 「俺も寝ないぞ?」 「…………え?なんで?」 「…………」 柳くんが眉根をよせてちょっと困った顔をしている。察しろ、とでも言うようなその風情に、数秒考え込んだ後「そうか!」とあたしは思い至る。柳くん勉強と部活で疲れてるもんね、そりゃーぐっすり寝たいわ。あたしが起きてたら気が散ってしょうがないだろう。 「大丈夫!あたしも寝るよ、安心して!」 ぽすっと顔にやわらかい感触を感じたら、どうやら枕を投げられたようだ。 「深夜の一人歩きといい、今の発言といい、はもう少し気をつけた方がいいな」 「?」 「行くぞ」と言って両手に防寒用の毛布を抱えて柳くんはさっさと二階へと上がっていった。 「うわー、本が一杯ある」 通された柳くんの部屋はシンプルな和室で、その端の立派な本棚に所狭しと装丁の古そうな本が収納されており、入り切らない本は床に積み上げられていた。「集めだしたらそれぐらいになっていた」とガラリと換気用に窓を少し開けながら柳くんは言う、その細面の顔に写るピンク色の薄い影。 「桜が見えるんだね、柳くんの部屋」 「ああ、時期的には今が一番見頃かもな」 窓にかけよって外を眺めれば暗闇に咲く夜桜が見事に満開だった。 「寛いでいろ、悪いが俺は湯を使わせてもらう」 「あっどぞ、おかまいなく、ていうかお風呂まだだったんだ、本当に突然上がり込んでごめんね」 「いい、気にするな、好きにみていろ」 「うん、ありがとね」 先程の熱いお茶ととろろそば越しの会話がそうさせたのか、緊張がとれてあたしも柳くんも妙に意識せず、くだけた雰囲気で話せるようになった。それともこの真夜中のしんとした深さがそうさせるのだろうか。 トントントンと柳くんが階下へ降りる音を聞きながら、ぐるりと八畳ばかりの部屋の中を見回す。勉強中だったのか、開かれたままの教科書と鉛筆が机の上にあり、 その横には学生鞄とテニスバッグが丁寧にかけられていた。立海大付属高校の制服が折り目も正しくハンガーの上でゆれている。開け放たれた窓から花びらが一ひら入り込んで、真新しい畳の匂いと古書の少しくすんだ茶に混じって、彩りを添えるようにゆっくり床に落ちた。 ここが柳くんの世界なんだな。 ここで柳くんは育ったんだな。 心のいとしい部分をぎゅっと掴まれたような思いで、そう思う。 本棚の近くまで行けば並んでいる本が純文学ばかりだという事に気がついた。色々あるなーへーあっこれ初版だ、すごい、小津安二郎の食についての随筆があるなーふーん好きなのかなー。そんな事をつらつらと思いながら眺めていたら、本棚に立てかけられている数枚の写真が目に飛び込んで来た。 「幸村くんと、えーと………真田くん?」 一枚目には、幼い面影のおかっぱ姿の柳くんと同じ様にあどけない顔の幸村くん、それと伏し目がちだけれど多分真田くん(最初わからなかった)だと思われる男の子達が、優勝旗を手に微笑んでいた。二枚目にはそれに仁王くんや丸井くんが加わって、他にも知っている人達がちらほらといて、高校の入学式当日にうちのクラスに遊びにきたあの元気なもじゃもじゃ頭の後輩くんもいた。三枚目は…なんだかちょっと全員が思い思いの読めない表情で写っていた。でもどこか落ち着いたような、ふっ切れたような、そんな風情で、口を真一文字にむすんだ後輩くんの目の端が赤い。中学時代の立海テニス部についてあまり詳しくは知らないあたしでも、その三枚の写真が織りなす彼らの歴史、そして無造作ながらも本棚にその写真だけを置いた柳くんの静かな想いの強さを感じ取って、心の中で「見ちゃってごめんなさい、でも皆すごく生き生きとしてて眩しいです」と小さく祈って、そっと本棚に戻した。 部屋の端っこに座って、渡された毛布にくるまりながら適当な本をぱらりと繰っていたら、タオルで頭を拭きつつ、柳くんが階段を上がって部屋に入って来た。 「くつろいでまーす」 「ご自由にどうぞ」 Tシャツに肌触りの良さそうなこざっぱりとした麻の部屋着姿で、柳くんは長い腕を伸ばして窓をしめた。均整のとれた二の腕がちらりと見えて、水分を含んだ黒い髪をつたい、しずくがぽつりと足元に落ちる。素足の踝の白さが、なんだか無防備だ。こんな多分、身内以外知らないような姿まで、垣間見てしまっていいのかな?と本越しにドキドキしたけれど、もう今さらだ、と思ってごろんと横になって本のページに視線を戻した。そのまま柳くんは机に座って、勉強の続きに向かいかけたけど、あたしの手元にある本に一瞬意識があわさっていたのがわかる、そういえばこの本あの三枚の写真の隣にあったやつだ。 「柳くん中学時代もテニス部だったんだね」 「ああ」 「ごめん、写真勝手に見ちゃった」 「いい、置いてあるものだ」 柳くんの横顔はお風呂上がりの濡れた乱れた髪に隠されて、ぼやけて見えるけど、あの写真の中の着実に成長して来た少年の顔だった。 「良い写真だね」 「そうか」 「うん、とくに、三枚目」 柳くんの視線は教科書に合わさったまま、その手元のノートの上で鉛筆がざらっと音をたてて止まった。 「なぜそう思う?」 「うーん、なんとなくだけど、なんかちゃんとしてた」 「幸村くんを囲んで、みんな前を見てた」 気配で柳くんが少し口の端を上げたのがわかる、途絶えていた鉛筆音がさらさらと優しく流れだした。 「はテニスについて知っているか?」 「ううん、全然」 「試合を見にくると良い」 「へー良いの?見たい見たい」 「夏にな」 なんで夏?と思ったけれど「楽しみだなー」と言ったあたしに柳くんは笑った。 純文学の本はなんだか難しくて、くるまった毛布はやわらかく暖かくて、頭上でゆっくりと流れる柳くんの鉛筆音は子守唄のようで、その足元で猫みたいに丸まったあたしは規則的な音にあやされるまま、うとうととしだした。 柳くんの部屋は居心地がよく、とても気持ちがいい。 どれぐらいの時間がたっただろう。寒い肩に何かがかけられた気配がして、ぼんやりと薄目をあけて見れば、柳くんの細長いきれいな手と膝をついた素足があった。やわらかく毛布をかけ直したその手が、あたしの髪についた色を摘んだ。一ひらの桜の花びらが、繊細そうな手の平におさまる。 この人を好きになるのはとても自然な事だな、と思った。 「柳くんだよ」 「ガールズトーク、あたし……柳くん派だったよ」 ふわりと白い指で瞼を撫でられた。 「おやすみ」 優しい声が落ちて あたしの意識はすべて、柳くんの世界に包まれた。 「……、」 「……ん」 チュンチュンと鳴く小鳥の声と、もう一つの静かな呼び声でガバッと慌てて起き上がる。目をこすって見れば、柳くんはもう制服に着替えて鞄に教科書をつめていた。 「あたし………寝てた?」 「ああ」 「ぐっすり?」 「ああ」 「……しまった」 「もうそろそろお前の姉も帰ってくる頃だ、両親が起き上がる前に戻った方が良いだろう」 「うん」 そぉ〜と洗面所を借り、顔を洗って玄関前に行けば柳くんもテニスバッグを担いでいた。今日はテニス部の朝練があるらしい。一緒に玄関を出れば、辺りはまだ薄暗かったけれど、清々しいまっさらな朝の匂いがした。昨日きた道をまた二人で戻るように歩く。 「柳くんは寝てないの?」 「そうだな」 「………ごめんね」 「謝らなくていい、かわりに面白い寝言を聞けた」 「え!?あたし何か変な事言ってた?」 「覚えていないのか?」 「………覚えてる」 「俺も覚えている」 そのまま駅前のコンビニ前であたし達は立ち止まった。昨日あたしと柳くんがばったりと出会って、そのままの縁で不思議な真夜中を一緒に過ごす事になった始まりの場所だ。夜はもう明けた、そして、これからはー……… 「本当にありがとうね、柳くん」 「」 「ん?」 テニスバッグを肩にして駅に向かおうとした長身が、あたしに振り向いて言った。 「今度は昼間に遊びに来い」 その声を聞いて、心の奥にふわふわとした嬉しさが募るのを感じながら、あたしはできるだけの笑顔で答える。 「スカート履いてくるよ」 「それはありがたいが、その格好でベランダからは飛び降りるなよ?」 「わかってるって、窓越しのお花見が良いな」 「俺の部屋でか?」 「うん、今度は夜桜じゃなくて」 「わかった、そうしよう」 「じゃ、また学校で」 「ああ、学校で」 細い背中が駅の改札口に消えるのを見届けながら、振り向かずにあたしは歩く。 その歩幅が騒ぐ心臓の音にあわせて、だんだんと大きくなって、だんだんと早まる。 笑顔がずっと消えない。 昨日の真夜中にひとりで空腹を抱えて走った坂道を、今度は「柳くんが大好きだ」という想いをいっぱい抱えて、ひゃっほーとあたしは春の朝へと駆け出した。 100407 |